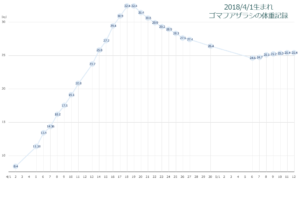いきもの情報(コブダイ)
日本海大水槽に「コブダイ(オス)」を展示していますのでお知らせします。

コブダイ(日本海大水槽,浅場)
◆コブダイSemicossyphus reticulatus(スズキ目ベラ科コブダイ属)
コブダイは、全長80cmほどまで成長する魚で、全身は赤色、オスの成魚では頭部が大きく張り出しコブがついているように見えるのが特徴です。
昨年末に寺泊で採集された個体で、日本海大水槽の浅場で展示しています。
当館では久しぶりの立派なオス個体の展示となりますので、この機会にぜひご覧ください。
コブダイは、「日本海大水槽」のほか、対馬海峡を越えてコーナーの「新潟の岩礁水槽」、黒潮洗う太平洋岸コーナーの「太平洋沿岸水槽」でも見られます。